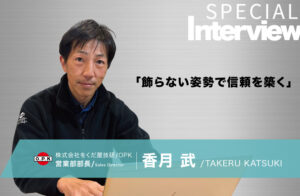登山と僕

最初の一歩は、大台ケ原だった
登山をはじめたのは、今からもう 10 年ほど前のこと。会社の上司に「山、行ってみるか」と誘われて、軽い気持ちでついて行ったのが大台ケ原だった。
装備はほとんど持っておらず、街用のリュックにトレッキングシューズ。“ザック”という言葉すら知らなかった。飲み物とおにぎりだけを詰めて、遠足の延長のような気分でいた。
ところが登り始めてすぐ、息は切れ、足は重く、木の根や石につまづくたびに「こんなに登山ってしんどいのか」と思い知らされた。それでも、山頂で食べた冷えたおにぎりが、驚くほど美味しかった。風に吹かれて眺める景色の中で、一口ずつ噛みしめるその味は、コンビニの棚で見たときとはまるで別物だった。
何がどう、というわけではないけれど──そのとき、「山っていいかもしれないな」と、素直に思った。
初めての釈迦ヶ岳と、夜の山
しばらくして、今度は釈迦ヶ岳へ。初めてのテント泊だった。必要な装備は、会社の同期に借りた。
何が何やらわからないまま、言われるがままザックに詰め込んだ。ザックはパンパンで、背中にずっしりとのしかかる重さ。登り道では何度も息を整え、膝に手をつきながら足を前に出した。
ようやくたどり着いたのは、山頂近くのテント場。そこでテントを張り、ひと息つくころには夕暮れが迫っていた。空の色がすこしずつ薄れていき、気がつけば、頭上の空よりも足元の森の方が先に暗くなる。空はまだ青みを残しているのに、森はすでに黒く沈んでいて、あのコントラストが印象的だった。
夜になると周囲は静まりかえり、夕飯の準備をしていると、遠くにぼんやりと、いくつもの光が浮かんでいた。
小さくて静かで、でも確かにこちらを見ているような気配。
誰かのライトでも反射でもない、不思議な光の正体は──鹿だった。
何頭も、じっとこちらを見つめていた。彼らにしてみれば、こちらが“珍客”だったのかもしれない。
そのあと、上司がひとりで湧き水を浴びに行ったのだが、しばらくして「ひいっ!」という悲鳴のような声が闇の中に響いた。あとから聞くと、想像以上に冷たかったそうで、それがまた妙に可笑しかった。その湧き水は本当に冷たくて、そして驚くほど美味しかった。
光も音もない、ほんとうに“静かな夜”。
不便さと隣り合わせの空間で、「これが今夜の自分のすべてだ」と思えた。
小さな火と、小さな食器と、小さな寝袋。
でも、それで不思議と心は満たされていた。揃ってはいない。でも、足りていた。
そんな感覚が、初めて心の中に芽生えた。

ごはんをつくる楽しさ
後輩がくれた小さなガスストーブ(バーナー)。最初にそれでお湯を沸かし、山の上で食べたカップ麺は、「あったかいって、こんなに沁みるのか」と思うほど体に染みわたった。
もともと僕はお酒を飲まないけれど、山で食べる温かい食事には、それに近いような“満たされる感覚”があるように感じた。ちょっと疲れて、お腹が空いて、風が吹く中ですする麺。それだけで、体も心もじんわり温まる。
そこから、少しずつごはんにも挑戦するようになった。できるかどうかはわからなかったけれど、試してみたかった。家でレシピを調べて、なるべくシンプルに、でもちょっと楽しみもあるように。パスタ、ポトフ、焼きそば、ホットサンド、ステーキ、お好み焼き、冷たいうどん。不思議なもので、限られた道具や食材の中でこしらえるごはんには、“つくる楽しさ”がぎゅっと詰まっていた。
登山の目的が、ただ登ることから、「食べてみる」「やってみる」というものに変わっていったように思う。
いつの間にか、山ごはんは僕にとってのちょっとした冒険になっていた。
荷物が減って、感覚が研ぎ澄まされた
登る回数が増えるごとに、ザックの中身は少しずつ減っていった。
最初は「念のため」と思って詰め込んだあれこれも、
いざ使わないとわかれば、次からは持って行かなくなる。逆に、「これは絶対必要だな」と思ったものは、多少重くても必ず入れる。選ぶという行為が、登山そのものになっていく。持ち物だけじゃなく、歩く道、時間配分、誰と登るか。一つひとつが自分の判断で決まっていく──その感覚が心地よかった。

高さじゃなくて、時間
最近は、なかなか山に行けていない。仕事も日々の用事もあって、週末がどんどん過ぎていく。
それでも、ふとした瞬間に山の空気を思い出す。
高い山じゃなくてもいい。絶景じゃなくてもいい。
近場の低山をのんびり歩いて、温かいご飯を食べて、風を感じる。
それだけで、心が整っていくような気がする。山は「高さ」じゃない。
流れる時間の濃さや、余白の豊かさこそが、山の魅力だと思う。
あくまでも僕自身がそう感じているだけで、標高を目指す登山のストイックさや挑戦心も、とてもすばらしいと思っている。ただ今の自分には、この“ゆっくりとした時間”がちょうどよかった。
少しだけ、仕事の話をすると
僕はいま、会社で開発の仕事に携わっている。一から十まで理想通り、ということはほとんどない。
時間も条件も限られていて、その中でどう進めるかを毎日考えている。
そんなとき、ふとザックを詰めている自分を思い出す。山では「全部は持っていけない」ことが前提だ。
限られたスペースと重さの中で、本当に必要なものを選ぶ。登山と開発、ぜんぜん違うようで、感覚はどこか似ている。手放すことで見えるもの、制約があるからこそ育つ工夫。
山で得たそのリズムは、仕事にも少しだけ息づいているような気がする。

おわりに
また時間ができたら、あのザックに荷物を詰めて、バーナーと小さな鍋を持って、山に行こうと思う。汗をかいて登って、風に吹かれながら、あったかいごはんを食べる。それだけで、また元気になれる気がする。
すべてを揃えなくても、足りないものがあっても、山は楽しめる。それに気づけたのは、山と出会ってからだった。
そしてそれは今も、僕の歩く日々の中に、ちゃんと残っている。
そういえば、山で食べたごはんのことは、まだあまり語っていなかった。あの話は、それだけで一つの旅のような気がしている。
そのうち、あらためて触れてみたい。
寄稿日:2025年7月
この記事を書いた人:
株式会社をくだ屋技研
開発戦略部 部長
磯貝 弘和/Hirokazu Isogai