「をくだ屋技研との出会いからスタートした、ものづくりの原点」──株式会社をくだ屋技研(OPK)

一筋に歩んだ40年、病床にあっても止まらなかった創業者の創意と発想—— 最後の瞬間まで多くを学ばせていただきました。
—市原専務は、もともとものづくりへのご関心が深かったのでしょうか?
もともとは飛行機の整備士になりたいという夢を抱き、高専への進学を目指したこともありました。結果的に大学では工学部電子機械工学科へと進み、電子と機械の双方を学びました。ものづくりへの関心は、その頃から変わることなく持ち続けています。
—をくだ屋技研との出会いについて教えてください?
大学時代は好奇心旺盛で、興味のあることに積極的に取り組んでいました。その結果、気がつけば4回生の11月、就職活動の終盤に差しかかっていたのです。就職課に残っていた企業の中で、偶然にも目に留まったのが「をくだ屋技研」でした。1985年、新卒として入社したのが始まりです。それ以来、今日に至るまで40年近く、ずっと叩き上げられてきました。
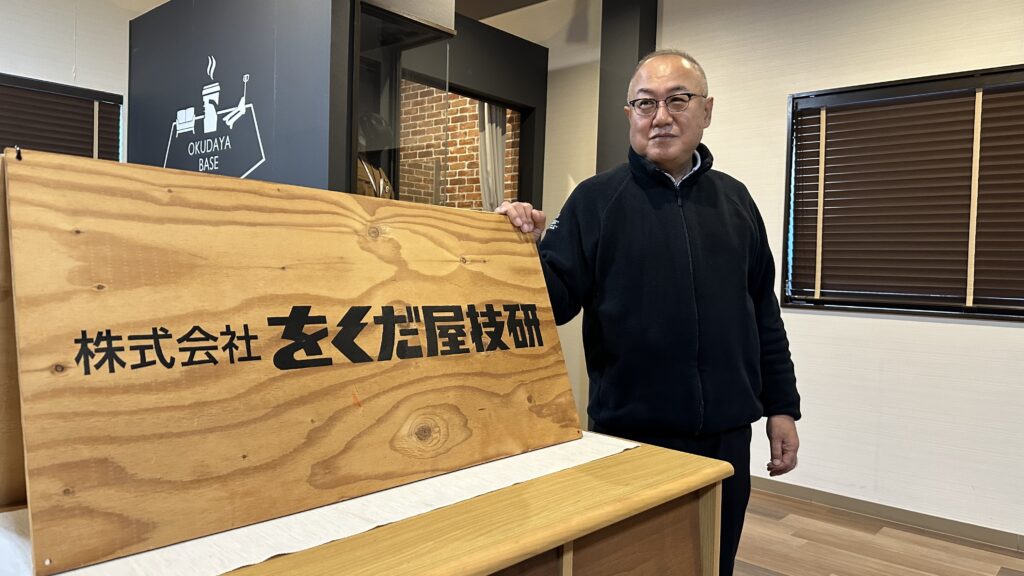
—他社への転職はご検討されなかったのでしょうか。
私の性格上、一途に物事に取り組む傾向がありまして(笑)。気付けば私も古株になっていました。
—入社当時と比べて、会社の雰囲気は変わりましたか?
大きく様変わりしました。私が入社した当時は、(インタビューした応接室のある)この建物のみで、その他は倉庫のような平屋ばかりでした。現在の総務部がある棟が事務所棟で、設計係は総務棟の一角にあり、私は技術系として開発係に配属されました。そこでは、池本係長を中心に、建築会社では見られないような鉄工屋顔負けの設備を自らの手で整備し、エアー配管の敷設や高所作業も行っていました。当時は「池本鉄工」と冗談を言われるほどでした。
—キャッチパレットの製造もその頃から始まっていたのですか?
当時は現在よりもはるかに少ない人員で、驚くほど多くの台数を製造していました。中国の産業が台頭する前の時代であり、アメリカなどへの輸出が盛んな時期でした。入社当時は、創業者である奥田源三郎社長(当時)のもとで、本当に多くのことを学ばせていただきました。技術的な指導からモノの考え方まで、とても厳しい面もありましたが、最後の最後まで発想することをやめない姿勢は圧巻でした。病床にありながらも頭は常に動いていて、「さすが経営者、さすが技術者だ」と尊敬の念を強く抱いたのを覚えています。
—経営者でありながら、技術者としても優れた方だったのですね。
まさにその通りです。名誉会長に就任された晩年、私が中国から帰任した頃には既にお身体も不自由でいらっしゃいましたが、それでも「自分が自由に入れるお風呂を作ってくれ」とご要望をいただき、多くのアイデアとスケッチを描かれました。結果として、いくつもの特許を取得されました。“発想を止めない姿勢”は、最後の最後まで私に大きな学びを与えていただきました。
■をくだ屋技研との出会いからスタートした、ものづくりの原点
現代は効率を重視した便利なツールがたくさん。
それでも発想力やひらめきは人間にかかっている。
—専務は海外でも多くの経験をされたとうかがいました。
ある日突然、当時の常務から「パスポートは持っているか? 明日から韓国へ行くぞ」と言われたこともありました(笑)。そこから次々といろんな国に同行し、各国のお客様からいただいたアイデアを持ち帰っては、自分で一生懸命に図面を書き、製品として納品していた時代がありました。
設計、検査、特機、生産技術など、さまざまな部門を経験しましたが、特に開発の仕事には強い愛着があります。自然と開発畑を歩むようになり、海外に一人で出向いて部品を調達したり、新しい技術を見つけては製品化につなげる役割を担うようになりました。
ヨーロッパ出張は“ご褒美”的な体験でしたが、当時はスマートフォンもなく、迷子になりそうになったことも度々ありました。
—中国では長期駐在もされていたとか。
約4年間、単身で駐在していました。現地に根ざして生活し、仕事をした経験は、私にとってかけがえのない財産です。言葉の壁もありましたが、生活するうえでは何とかなる程度にはなっていきました。
—言葉の壁といえば、中国語は難しそうですね。現地の言葉を覚えるきっかけになった出来事は?
まさにそこが大変でした。中国語の標準語である“普通話(プートンファー)”が基本ですが、地方へ行くと方言のバリエーションが多く、内容の理解に苦労しました。北京語と広東語でもかなり異なりますから。
今はそれなりに話せる程度ですけどね。現地の言葉を覚えるきっかけになったのは、キャッチパレットトラックやアンティエースの開発でした。特にキャッチパレットトラックのモデルチェンジの際、ハンドルを樹脂製に変えることになり、その部材を作ってくれる業者を探し回ったんです。アリババで・・笑。最終的に上海の会社にお願いすることになったのですが、当時の私は中国語がまったく話せませんでした。それでも一人で何度も通い続けるうちに、少しずつ勉強して話せるようになったんです。
その苦労の末に完成したキャッチパレットトラックは、ODC(大阪デザインセンター)から声をかけていただき、ODC賞やグッドデザイン賞を受賞しました。たしか2007年頃だったと思います。ハンドルのデザインに丸パイプを採用したのも源三郎名誉会長のこだわりの一つです。あまり知られていないことですが(笑)。


—心に残るプロジェクトになったのですね。
心斎橋のクリスタ長堀にも展示していただきました。自分たちの努力の結果が形になったことに対し、「よくやったな」と誇りを持てる仕事の一つです。
—プロジェクトのスタートはどんなところからだったのでしょうか?
東京の営業担当から「やっぱりハンドルは樹脂のほうが良いのではないか」と提案されたのがきっかけでした。今のように3Dプリンターなど便利な道具はなく、まずはお金をかけて木製のモックアップを作り、イメージを共有していきました。 さらにその前段階では3DCADすらなかった時代で、粘土を使ってハンドル形状を仕上げました。当時の係長と二人で粘土をこねながら「どちらがいいか」と真剣に相談して決めたものです。
—大学時代の経験も活かされていますか?
そう思います。理系の学生だった私は、週ごとに実験や図面、レポートに追われていました。今では想像しづらいですが、当時はT定規を使って製図をしていました。製図板にT字型の木を当てて線を引き、三角定規を駆使して角度を出す、そんな完全な手作業でした。 卒論も日立のワードプロセッサーで書いたんですよ(笑)。
—現在はCADも活用されていますか?
今でもたまに使いますが、学生時代のような手作業での経験が、今でも発想や構造理解の礎になっています。当時はレポートもすべて手書きで、しかもボールペン。ミスをすれば修正液で直すしかない。今は便利な時代ですが、あの時代の苦労は決して無駄ではなかったと思います。
—今のほうが効率的ではありますよね?
確かに便利にはなりました。しかし、昔はドラフターで一本ずつ線を引いて、図面一つ仕上げるにも時間と工夫が必要でした。そのプロセスが、結果として豊かな発想につながっていた。現代では、CADで画面上に線を引くだけで形になりますが、それだけでは十分な発想力が伴わず、結果的に効率が悪くなることもあるのです。
本当に効率を求めるなら、まずはしっかりと考える。その上でCADやAIといったツールを活用するべきだと思います。それが人の成長にもつながり、結果として製品の完成度も向上するのではないでしょうか。
—かつての、限界があったツールゆえに磨かれた技術や感覚があると?
当時は「もう大変や!」と苦労ばかりでしたが、それでも時間をかけて作り上げたからこそ、良いものができたという実感がありました。現在は作業効率こそ上がっているかもしれませんが、出来上がったものを比較すると、どこかに漏れがあったり、実際の製造工程で不具合が出てくることも少なくありません。
たとえばCADで正確に線を引いたとしても、現実の製品はその通りには仕上がらないこともあります。ピッタリすぎて動かないとか、もう少し“遊び”が必要だったりする。昔の技術者たちは、そういった感覚や知恵をしっかり持っていました。そういった“間”や“余白”を大切にする感覚を、現代でも育てていく必要があると思います。
—現場で肌感覚として感じる部分ですね。
図面では完璧に見えても、実際にはうまくいかない。だから、伝えたとしても、その“なぜそうするのか”を理解するまでには時間がかかるんです。昔の図面はすべて手書きで、場合によっては図面を切って貼って、構成し直したりしていました。そういった工夫や手間を惜しまず積み上げていくプロセスが、今のものづくりには必要なんです。
ロボットなど最新技術は、模倣や作業スピードに優れていますが、創意のプロセスが抜け落ちていることもある。日本人は“コツコツ積み重ねる”という文化を大事にしてきました。それは“面倒くさい”と言われるかもしれませんが、その丁寧さこそが良いものづくりの根幹だと私は思います。

■実際に現地で学んだ、共に働いたから叶った海外グループとの絆
—オウンドメディア「OKUDAYA CONNECT」が始まりました。海外グループとの交流を深めていくことについて、どうお考えですか?
駐在していた頃からの夢でもあり、一つの課題として感じていたのが「OPKグループが一堂に会する機会を作ること」でした。実際に現地で仕事をしないと分からないことはたくさんありますし、日本でそれを伝えようとしても、なかなか伝わりきらないものなんです。
それでも、海外のスタッフたちは見えないところで、OPK製品のために懸命に努力してくれています。だからこそ、そうした現地の様子を日本でも共有できる場が必要だと強く思っています。先日も中国を訪問し、多くのメンバーと再会できました。やっぱり、人は人と会うことで元気になるんですよね。
—現地のスタッフにはどのような印象を持たれましたか?
中国には、立ち上げ当初から一緒にやってくれている副総経理のスーさんという方がいます。彼女は「OPKという会社が自分の人生を救ってくれた」とまで言ってくれていて、何かトラブルが起こったときにも、最前線に立って見えないところで工夫を凝らしてくれます。
中国の2つの工場を統合するという計画があったのですが、なかなか進まなかった。でも、ミーティングを重ねて「よしやるぞ!」とみんなの気持ちが一致した瞬間からは本当に早かった。日本でやれば数カ月かかるようなことを、1カ月でやり遂げてしまったんです。そのとき、李総経理・蘇さんや呂さん皆さんの尽力で、OPKに対する理解と愛着の深さを改めて感じました。
—中国ならではの文化やエピソードがあれば教えてください。
日本ではあまり見かけませんが、中国では一つの仕事が成功したら、ハグをするんですよ。取引先の総経理とも、自然とそうなります。「最近太ったか?」なんて言いながら(笑)。
中国はとにかく“人と人のつながり”が大切にされている文化です。私たちが現地を訪れると、数時間かけてでも駆けつけてくれる。「あなたが来たから、私も来た」と言ってくれるんです。日本に台風や災害が来たときにも、「大丈夫か?」と電話をくれたりする。家族のような絆が自然と生まれる場所ですね。
—仲間としての信頼関係が築かれているのですね。
私たちは技術者なので、図面が共通言語になります。あとは表現力次第。たとえ中国語の単語を適当に並べて話しても、気持ちが通じれば理解し合えるんです。波長が合えば、言葉以上に通じるものがあります。
■ をくだ屋技研の100周年を目指して、改めて伝えたいこと
—では、仕事をするうえで、市原専務が大切にされている価値観やモットーを教えてください。
一言で申し上げると、「人との出会いを大切にすること」と「自分で必ず確かめること」の二つです。海外駐在時も日本国内でも、私は一人でご飯を食べに行くことが多く、そうした場面で隣に座った方と自然と会話が生まれたこともたくさんあります。そこからビジネスや開発のヒントが生まれることもありましたし、何より人との出会いから得られる元気や刺激は大きいと実感しています。
そして、もう一つの「自分で必ず確かめること」も、非常に重要だと思っています。何事にも自ら興味を持ち、発想やひらめきを鍛える。そして、それを形にしていくなかで、最後は必ず自分自身の目で確かめる。この積み重ねこそが、自分を成長させ、ものづくりの根幹を支えてきたと感じています。

—最後に、読者の皆様へメッセージをいただけますか?
海外にもグループ会社を持つをくだ屋技研は、特に2020年以降のコロナ禍において、多大な影響を受けました。それだけでなく、世界情勢の急激な変化や各国の法改正など、目まぐるしい環境変化にも直面してきました。
そんな中でも、社員一人ひとりの努力と連携によって、なんとかここまで踏ん張ってこられました。これは本当に、関わってくださっているすべての皆様のおかげだと心から感謝しています。
現在、マレーシアは創業から30年を超え、中国は2026年に20周年を迎えます。そして私たちOPKグループも、次に迎えるのは95周年、そして100周年という大きな節目です。
まだまだ課題は山積していますが、OPK全体が一丸となり、各国の歯車がしっかりとかみ合ったときには、きっと大きな力を発揮できると確信しています。そのきっかけを作るのは、私たち経営層の責任でもあります。
これからも、あきらめず、くじけず、皆で力を合わせて、大きな成長へとつなげていきたいと思っています。今後とも変わらぬご支援を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
取材日:2025年9月
インタビュー協力:
株式会社をくだ屋技研
専務取締役 市原 浩一











